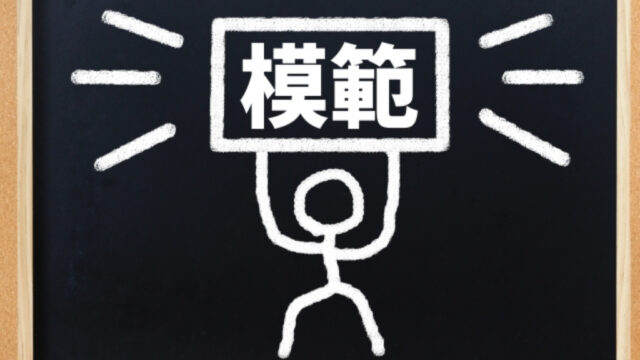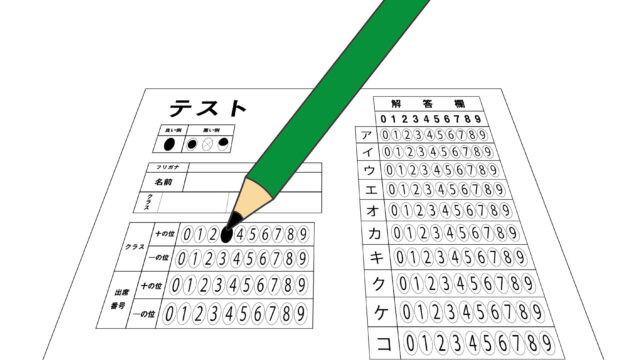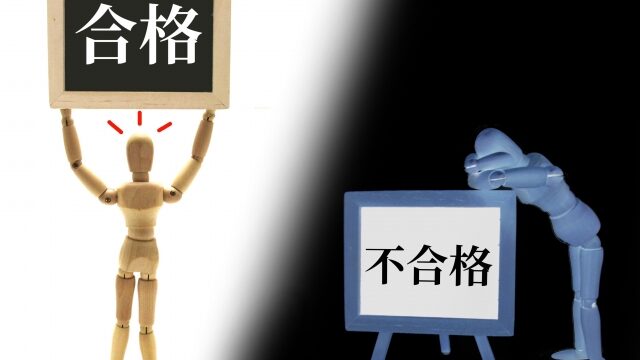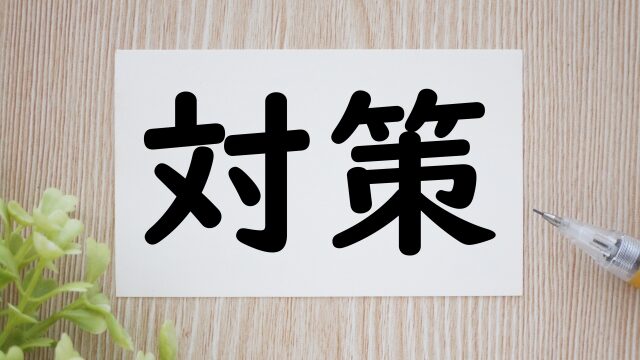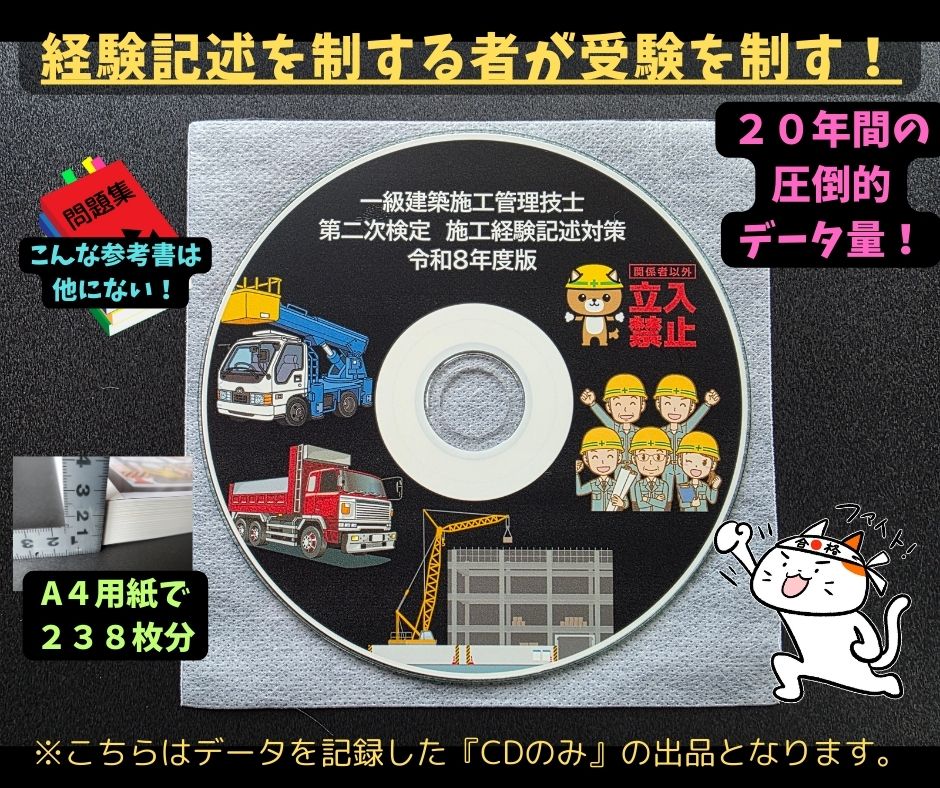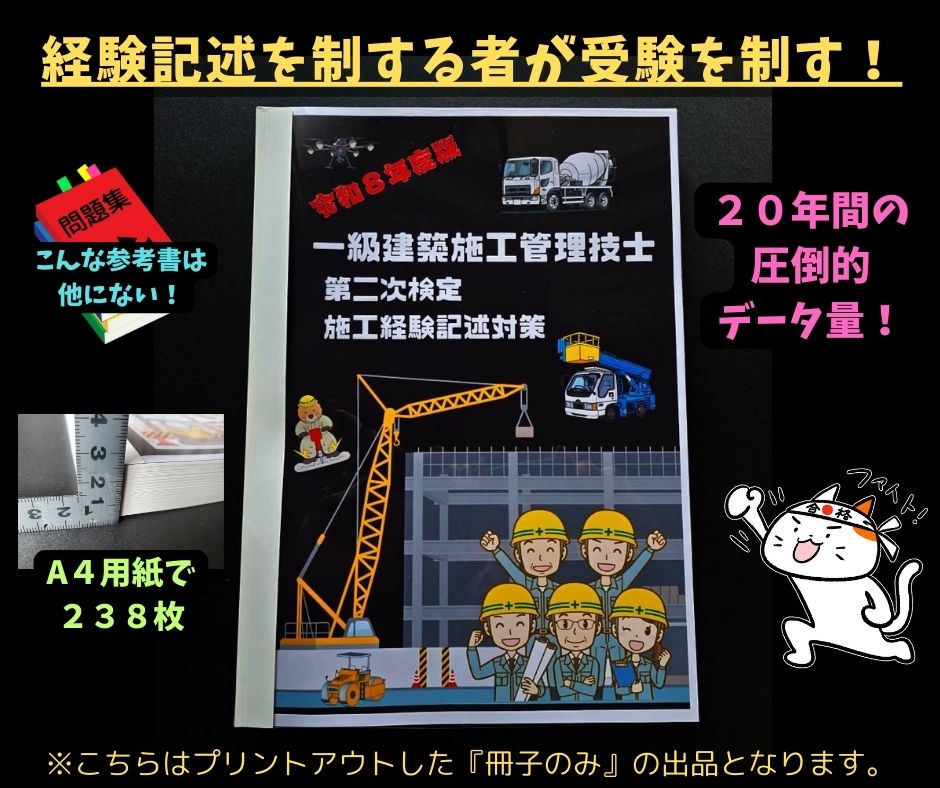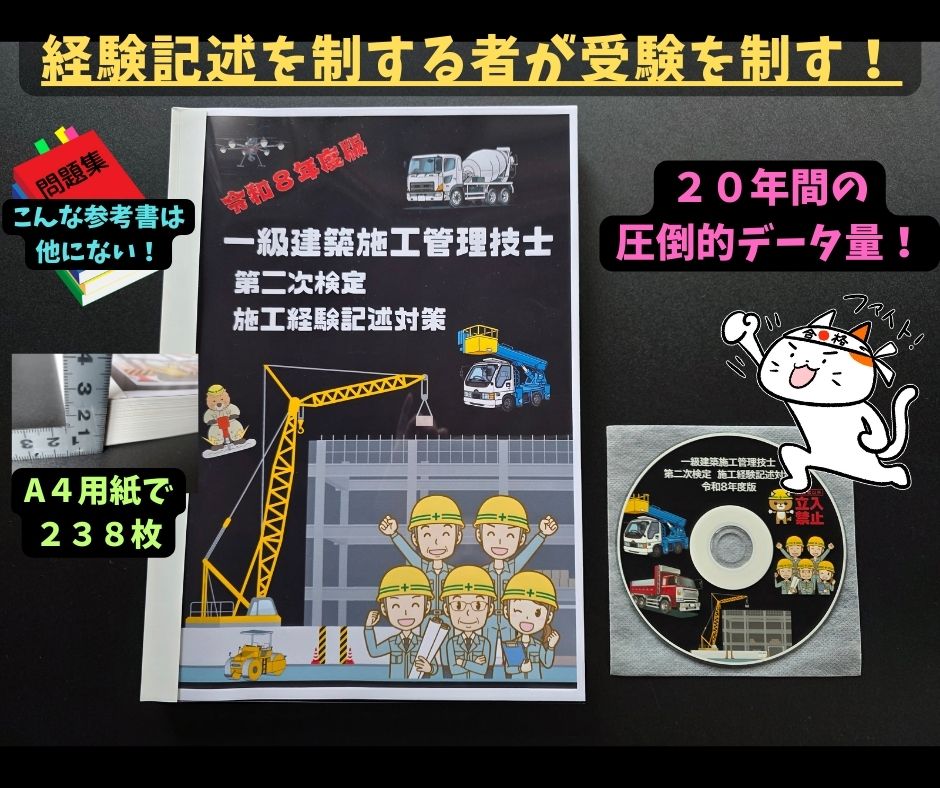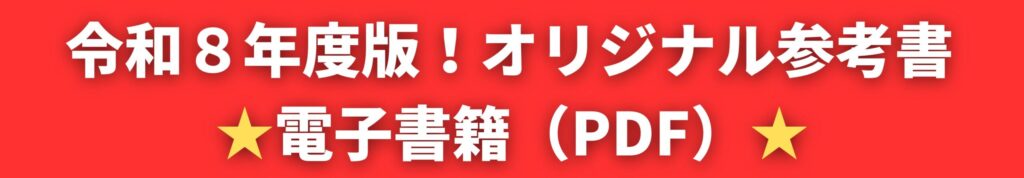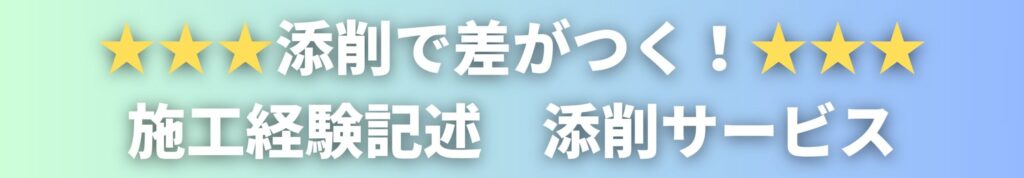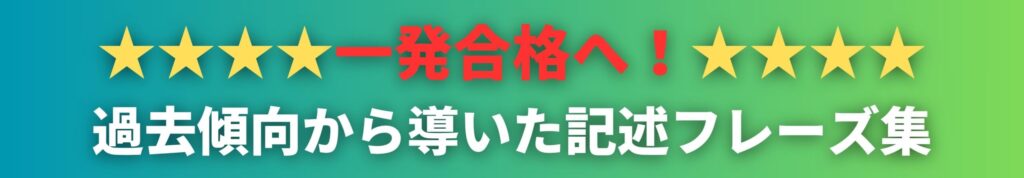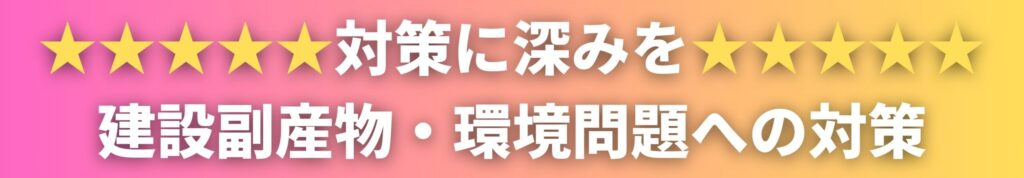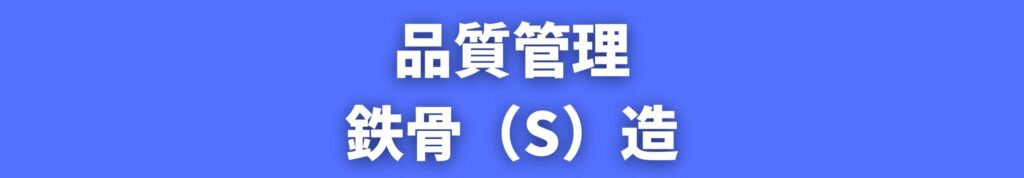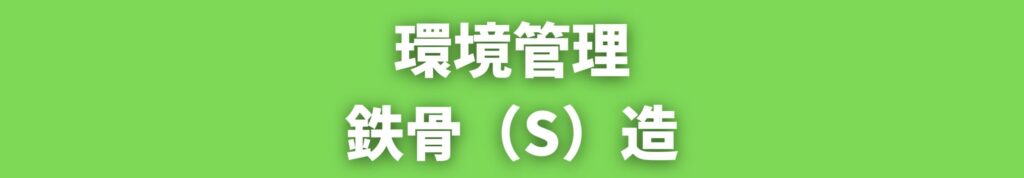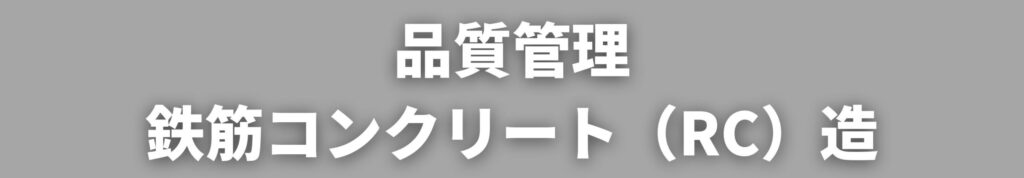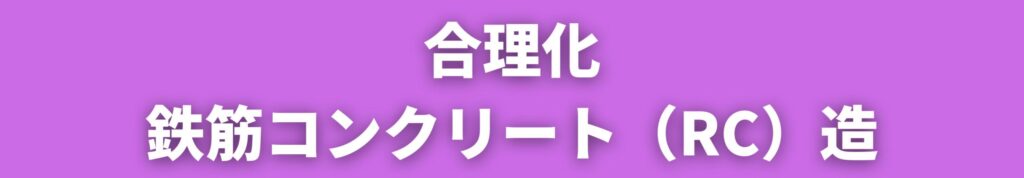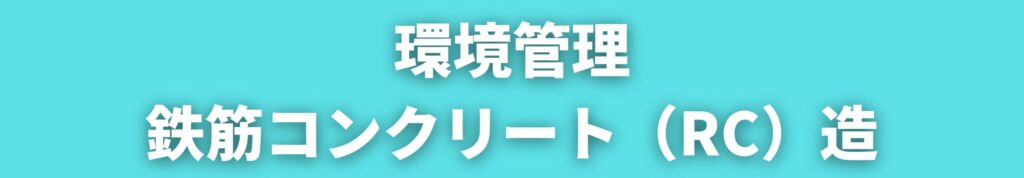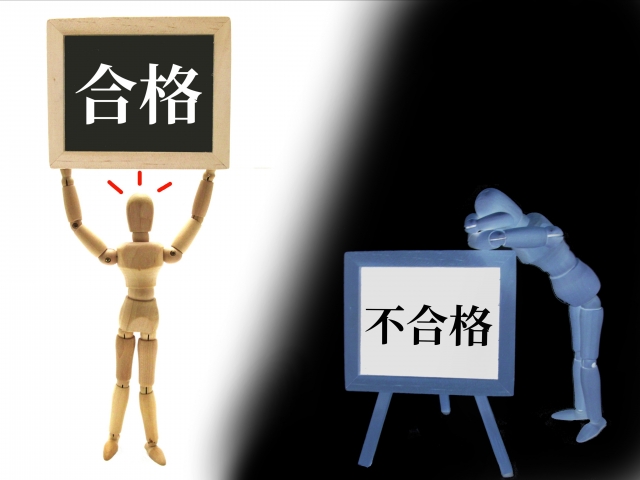施工経験記述の合格体験記は先輩からの貴重なアドバイス、そして、木造建築しか経験がない方も諦めないで。

一級建築施工管理技士の第二次検定における「施工経験記述」は、合否を大きく左右する最重要パートです。
本ページでは、実際にこの経験記述に合格した方の体験談を掲載しています。
書き出しの工夫や、キーワードの入れ方、時間の使い方など、成功のヒントが満載。
これから経験記述に取り組む方は、ぜひ参考にしてください。
年代別の合格体験記(20~50代)+木造建築の経験しかない方
合格体験記(20代)
● プロフィール
20代後半・中堅ゼネコン勤務・学科同年合格・現場経験3年
● 経験記述で一番悩んだこと
とにかく経験が浅くて、「書ける現場があるのか?」と不安でした。さらに自分のやったことに自信もなく、全部上司にやってもらった気がして…。
● どうやって書けるようになったか
日報と写真をもとに、自分がやった「段取り」や「確認作業」を整理してみたら、意外と書けることがあると気づきました。「現場代理人じゃなくても管理はできる」と添削で教わったのが大きかったです。
● 添削の効果
「成果が曖昧」「主語が抜けている」など、自分では全然気づかなかった点を指摘されました。それから、文を直すだけでなく、考え方そのものが変わりました。
● 使った教材・参考サイト
会社の工事記録、施工管理技士の過去問、YouTubeの講義動画、当サイトの例文ページ
● これから受ける人へ
経験が少なくても、「自分がやったことを具体的に書く」ことに集中すれば大丈夫です。そして、難しく考えすぎず、まずは書いてみること!
合格体験記(30代)
● プロフィール
30代前半・ゼネコン勤務・学科合格済・現場経験10年
● 経験記述で一番悩んだこと
最初は「どの工事を書いていいかわからない」状態でした。品質管理と安全管理、合理化、どれにしても中途半端で…。
● どうやって書けるようになったか
自分の現場写真を見返して、具体的な工夫やトラブル対応を掘り起こしました。たとえば、キーワード(たとえば「施工手順の標準化」や「是正指導」など)を意識的に入れるようにしました。
● 添削の効果
最初に書いた文章を、添削してもらったら「誰が何をしたかが伝わらない」と言われて衝撃を受けました。そこから主語と動詞を明確にする意識が変わりました。
●使った教材・参考サイト
過去問3年分、自社の手順書、ネット上の体験談、当サイトの例文集
● これから受ける人へ
「努力しました」「注意しました」だけでは絶対に通りません。つまり、行動と効果を具体的に書くことが一番大事です。
合格体験記(40代)
●プロフィール
40代前半・地方ゼネコン勤務・学科合格後2年目で再挑戦・現場経験18年
●経験記述で一番悩んだこと
これまでの現場経験が多すぎて、どれを書けば一番伝わるのかが難しかったです。そして、「書きたいこと」より「評価されること」が何なのかが分かりにくくて…。
● どうやって書けるようになったか
評価基準を見直し、「トラブル対応」「是正指導」「改善結果」が含まれている経験に絞りました。自分が「段取りだけでなく、判断もしていた」と気づけたのがきっかけです。
● 添削の効果
主語が「私」になっていない文が多く、読んでも誰がやったかわからないと指摘されました。そして、そこを意識して直すことで、一気に通る内容になりました。
● 使った教材・参考サイト
社内資料、手順書、当サイトの例文、体験記ブログ
● これから受ける人へ
経験があるからこそ、自分では当たり前と思って書かない部分が評価に直結します。つまり、第三者目線で書くことが大事です。
合格体験記(50代)
● プロフィール
50代・建設会社の所長・学科免除・現場経験30年以上
● 経験記述で一番悩んだこと
書くのがとにかく久しぶりで、「日本語としてどう書いたらいいか」が不安でした。現場のことは分かっているのに、書こうとすると何も出てこない…。
● どうやって書けるようになったか
まずは口頭で誰かに説明してみて、それを録音して文字に起こしました。結果、経験があるからこそ、順序立てて話せば文章化しやすかったです。
● 添削の効果
「抽象的な表現が多すぎる」と言われたことで、何をどこまで書くかの目安が分かるようになりました。そして、「書かないと伝わらない」という感覚は添削で初めて得た実感です。
● 使った教材・参考サイト
昔の現場日誌、施工計画書、当サイトの事例
● これから受ける人へ
文章が苦手でも、現場経験がしっかりあるなら必ず書けます。そして、誰かの力を借りてもいいので、諦めずに取り組んでください。
合格体験記(木造建築の経験しかない方)
●プロフィール
30代前半・工務店勤務・木造住宅専門・RC造などの経験なし・学科と同年合格
●経験記述で一番悩んだこと
施工管理技士の試験は「大きな現場の話が必要」だと思い込んでいて、木造住宅ばかりの自分に書けることなんてないと思っていました。そして、施工図や工程管理も、ほぼ現場監督一人でやっているような現場なので「この程度の経験で通るのか?」という不安が大きかったです。
● どうやって書けるようになったか
調べていくうちに、「規模よりも管理の中身が評価される」と知りました。たとえば、品質管理なら「接合部の金物の確認」「ホールダウン金物の締付チェック」、安全管理なら「仮設足場の点検」など、小さな現場でもちゃんと管理していた場面がいくつもありました。
現場写真や過去のLINE報告、納まり検討の資料などを見返しながら、つまり、自分の判断で動いた場面を中心に整理して書いていきました。
● 添削の効果
最初に書いた文章では、評価される視点が抜けていると指摘されました。つまり、「確認した」とだけ書いていても、なぜ確認したのか、結果どうなったのかがないと伝わらないんだなと気づきました。
また、木造ならではの管理ポイント(例:防蟻処理、防水紙の施工確認など)もきちんと管理として通用することを知り、安心して書けるようになりました。
● 使った教材・参考サイト
自社の現場記録、現場写真、当サイトの例文、書き方ガイド動画
● これから受ける人へ
RC造や鉄骨造の経験がなくても、木造の現場で真剣に取り組んできた人なら合格できます。そして、経験の規模よりも、現場で自分が「なにを考え、どう対応したか」が伝えられるかがカギです。臆せず、まずは書いてみてください!
まとめ
一級建築施工管理技士・第二次検定の施工経験記述は、「現場経験の豊富さ」や「大規模工事の実績」が絶対条件ではありません。
そして、今回ご紹介した体験記からもわかるように、
- 経験が浅くても、現場での気づきや工夫を正確に書ければ合格できる
- 経験が豊富でも、「読み手に伝わる表現」に直すことが合否を分ける
- 木造住宅や小規模工事でも、自分の管理業務を具体的に記述すれば評価される
といった共通点が見えてきます。
つまり、「何をやったか」よりも「どう書いたか」が、合否を左右しているのです。
自分には書けることがないと感じている方こそ、まずは小さな経験からでも言葉にしてみてください。
もし迷ったら、添削サービスや例文集を参考にしながら、少しずつ自信をつけていきましょう。
✨✨✨ LINE限定で記述用テンプレを無料配布中!✨✨✨

令和8年度版のオリジナル参考書が完成しました!
手元に参考書が欲しいという方は下記サイトで販売をしています。
A4用紙で238枚分というかなり濃い内容となっています。
※参考書には、このサイトに掲載がされていない情報も沢山載っています。
どこでご購入をされても内容は同じです。
『一級建築施工管理技士』で検索をして下記の画像を探してください!
📩 商品の直接購入をご希望の方は、[こちらのフォーム]からお問い合わせください。
お急ぎの方はデータでの販売も行っています。
※ご購入にはPayPalアカウントが必要です。まだお持ちでない方は、事前に無料登録をお願いいたします。
Paypalの新規登録・利用(無料)はこちら⇒ Paypal公式サイト
掲載内容
1.出題の見直し2年目で出題のパターンが見えた?
令和6年度から記述問題の出題形式が見直され、過去2回の試験を経て、令和8年度で3年目を迎えます。この2年間の出題傾向から、一定のパターンや対策の方向性が見えてきました。本書では、それらの傾向をふまえ、令和8年度に向けた記述対策のポイントを整理しています。
2.過去20年の出題傾向
年度ごとに詳細をまとめました。これをじっくりと分析することで、これまでの流れが見えてくるはずです。さらに、その流れを読み解けば、次年度にどのようなテーマが出題されやすいのかを予測する手がかりになるかもしれません。
3.平成18年度~令和7年度の本試験解答例
試験対策として過去問を理解することは基本です。そして、令和6年度に第二次検定の見直しが実施されましたがそれでも過去問を捨てることは出来ません。繰り返し見ていると、どういうところが設問として出やすいのか見えてくると思います。そして、2年目で試験の傾向が見えたことから、令和7年度からの解答例数を大幅に増やしました。これに勝る試験対策はありません。
4.構造種別 経験記述例
新築工事において特に重要な、主要構造の3種類(鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造)に関する施工例を豊富に取り揃えています。さらに「おまけ」として、新築工事だけでなく改修工事に関する施工例も追加しました。
5.業種別 重点対策問題
受検者には、専門工事業の方が多い現実を踏まえ、この参考書では全17業種にわたる解答例を準備しました。そして、実際の施工現場を想定した具体的で実践的な内容により、各業種ごとの特徴を踏まえた解答を分かりやすく解説しています。
6.一問一答式
試験対策に役立つ解答の「引き出し」として、知識を効率よく整理できる一問一答形式の内容を加えました。そして、この形式では、試験で問われやすい内容を厳選し、要点を簡潔にまとめています。忙しい受検者の方でも、スキマ時間を活用して効率的に学べる工夫を盛り込んでいます。
7.良い記述例・良くない記述例
同じ内容でも、記述の仕方一つで採点者に与える印象が大きく変わります。さらにこの章では、採点者の視点を意識した「良い記述例」と「良くない記述例」を比較しながら、効果的な表現方法を学ぶことができます。
8.施工経験記述はこの3つ!
施工経験記述の出題傾向を分析した結果、対策すべき課題は3つに絞ることができます。そして、これら3つのテーマごとに、出題ごとの解答の注意点や重要な記述のポイントをまとめています。この章を読み込むことで、施工経験記述の対策は万全です。
9.令和8年度予想問題 鉄骨(S)造・鉄筋コンクリート(RC)造
令和6年度は「鉄筋コンクリート(RC)造の合理化」、令和7年度は「鉄骨(S)造の品質管理」でした。この章では鉄筋コンクリート(RC)造、鉄骨(S)造での品質管理・合理化・環境管理それぞれ6パターンでの設問と解答例を考えてみました。ヤマを張ることはオススメ致しません、しかし対策は必要です。
過去問データからの施工経験記述対策
- 出題の見直し2年目で出題のパターンが見えた?
- 過去20年の出題傾向
- 施工経験記述 過去19年分の本試験解答例
- 構造種別 施工経験記述例
- 業種別 重点対策問題
- 施工経験記述 解答参考例
- 応用問題が出ても怖くない!一問一答式で対策
- 建設副産物・環境問題への対策から経験記述を考える
- 施工経験記述の良い書き方・良くない書き方
- 独学でも出来る!施工経験記述はこの3つ!
記述対策に活かせる実例・体験まとめ
応援サポート教材(有料)
最新の施工経験記述対策メニュー
1.鉄骨造パターン
2.鉄筋コンクリート造パターン
二次試験へ向けて有効活用致しましょう♪
市販の参考書も加えるとより効果的!